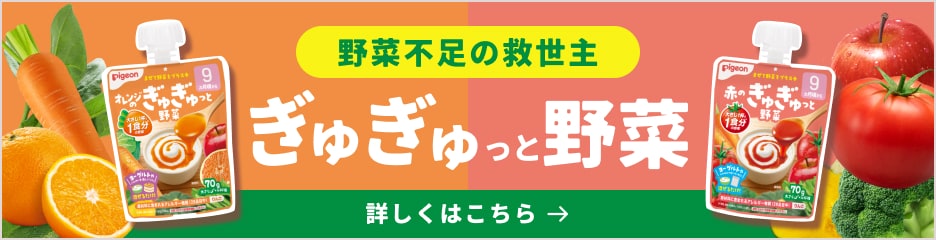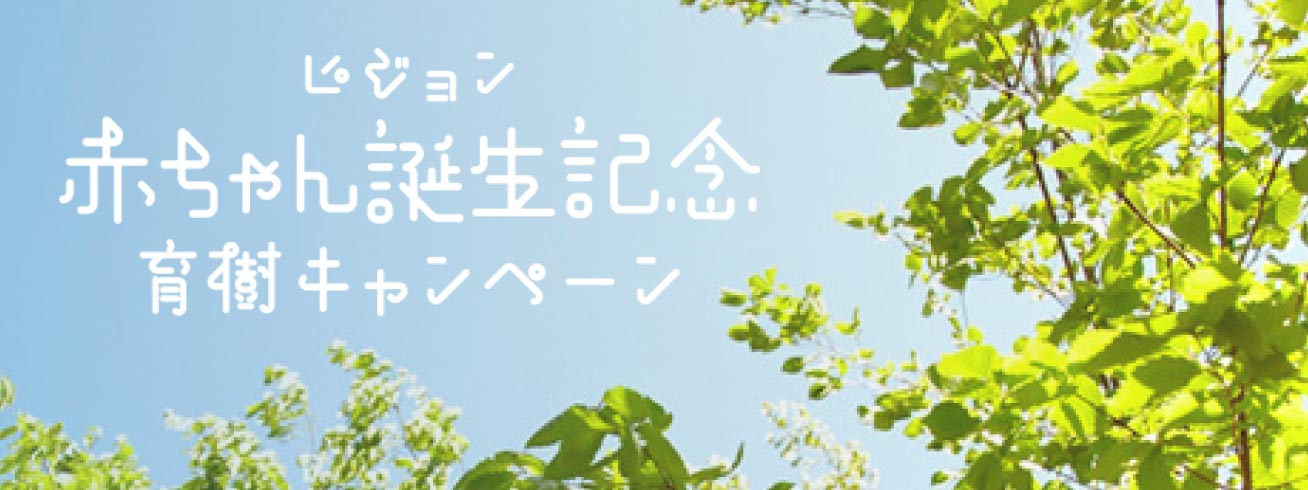ご飯や肉、魚はよく食べるのに、
野菜だけ食べない……。
そんなお子さんはめずらしくありません。
でも、野菜不足による健康への影響を考えると、親としては心配ですよね。ここでは、野菜嫌いの子どもが楽しくおいしく野菜を食べられるようになる方法をご紹介します。
調理法や声かけの工夫など、親子で楽しみながら取り組めるアイデアをまとめました。
1.子どもが野菜を食べない原因
そもそも、子どもが野菜を嫌がるのはなぜ?
おもに2つの原因が考えられます。

野菜は子どもが本能的に嫌がる
味だから
私たちが舌で感じる味は、「甘み」「うまみ」「塩味」「酸味」「苦み」の 5つに分類されます。このうち、「甘み」「うまみ」「塩味」は人間が生きるために必要なものであるため、おいしく感じられます。
一方、「酸味」は腐敗のサイン、「苦み」は毒のサインとされ、本能的に恐怖や危険を感じやすい味です。緑の野菜にはこの「苦み」が多く含まれているため、子どもが本能的に嫌がる味になっています。大人からみると好き嫌いや偏食は、子どもにとっては生存のために備わった本能的なリスク回避の大切な仕組みなのです。
野菜が食べにくいから
野菜は繊維が多く、乳歯が生えそろう3才頃までは子どもにとっては食べにくく、のどに詰まらせやすい食材です。特に繊維質の多い葉物野菜や硬い根菜は、噛むだけで疲れてしまうことも。また、独特の食感や固さが口の中で不快に感じられ、それが野菜嫌いの原因になることもあります。

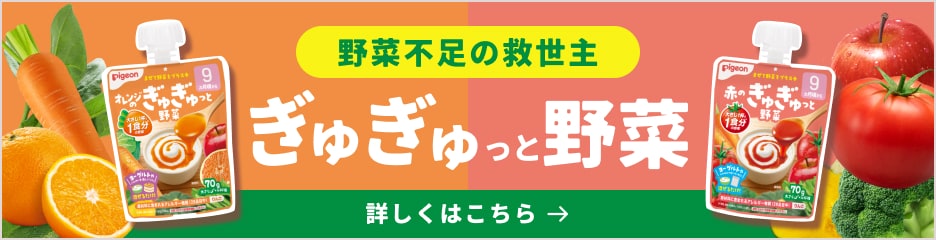
2.野菜を食べないとどうなる?
野菜には、体の機能を支える重要な栄養素であるビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。特に、視力の発達に必要なカロテン(ビタミンA)、免疫力を高めるビタミンC、体内調節を助けるカリウムなどは、子どもの成長と健康を支えるために欠かせません。
これらのビタミンの多くは体内で作ることができないため、食事からしっかり摂ることが大切です。野菜にはビタミンだけでなく、ミネラルや食物繊維もたっぷり含まれており、体に必要な栄養をバランスよく補うのに役立ちます。だからこそ、野菜を通じてビタミン・ミネラル・食物繊維を摂ることは、子どもの健康を守るためにとても重要なのです。
野菜を食べないとどうなる? 子どもが1日に必要な野菜の量は?

野菜不足になると、必要な栄養素が足りなくなり、免疫力が低下して風邪や感染症にかかりやすくなることがあります。また、ビタミンやミネラルが欠乏すると、成長の遅れや骨の発達に影響を与える可能性もあります。さらに、食物繊維が不足することで便秘だけでなく免疫力低下も招きやすくなります。
離乳後期(9~11ヵ月)の子どもに推奨される野菜・果物の摂取量は、1回あたり30~40g、1日あたり90~120gです。離乳完了期(12~18ヵ月)になると、1回あたり40~50g、1日あたり120~150gが目安とされています。生野菜120gの具体例としては、中サイズのトマト約1個、ブロッコリーなら小房5~6個程度に相当します。
この量は、小さなお子さんには「多い」と感じられるかもしれません。
- 離乳後期 (9~11ヵ月)
-
 推奨される
推奨される
野菜・果物の摂取量野菜:20~30g
果物:10g程度- 1回あたり
- 30~40g
- 1日あたり
- 90~120g
- 離乳完了期 (12~18ヵ月)
-
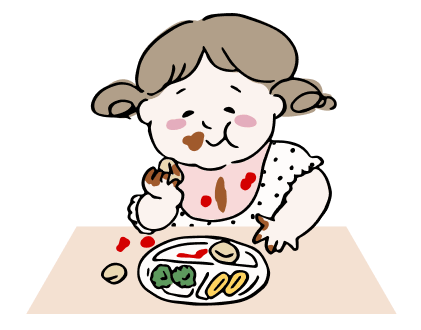 推奨される
推奨される
野菜・果物の摂取量野菜:30~35g
果物:10g程度- 1回あたり
- 40~50g
- 1日あたり
- 120~150g
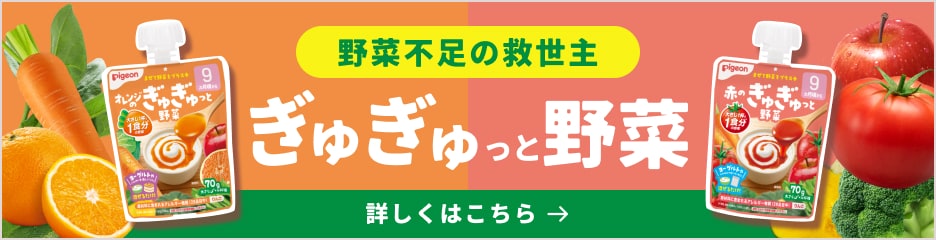
3.子どもに野菜を食べさせる方法は?
成長とともに野菜嫌いは自然に減少していきますが、時間がかかります。それまでの間にも野菜不足を少しでも解消したいですよね。子どもが野菜を食べるための工夫をチェックしていきましょう!
POINT01 苦くても酸っぱくても、安全な食べ物があると共食で学ぶ機会を増やす
子どもは本能的に、命の危険を感じて、苦味や酸味を避けようとします。しかし、共食を通じて、野菜や果物などの安全な食べ物があることを学ぶことができます。
家族と一緒に食卓を囲むことで、大人が苦味のある野菜をおいしそうに食べたり、甘酸っぱい果物を「おいしい」と言いながら食べたりする姿を見て、「自分も食べてみようかな」という気持ちが芽生えます。はじめは口から出してしまっても、少しずつ食べられるようになり、食べ続けることで好きになる習性が人間にはあります。そのため、成長とともに食べられるようになることが多いのです。

共食は、子どもの食の幅を広げる重要な機会です。子どもを一人で食事させるのではなく、家族や友達と一緒に食べることで、さまざまな食品にチャレンジする機会が増え、好き嫌いが解消されやすくなります。
POINT02 食べやすい形状にする

大きな野菜や形がゴツゴツしていると、「食べにくそう」と感じることがあります。小さく切り、形を整えることで、子どもが「これなら食べられそう」と思いやすくなります。また、固い野菜や繊維が多い野菜は噛むのが難しく、食べづらいと感じることも。茹でる、蒸す、ペースト状にするなどで柔らかくすると負担が減り、食べやすくなります。
POINT03 食べやすく調理する
細かく刻んだりすりおろしたりして豆腐ハンバーグや野菜あんかけ丼の具に混ぜたり、ほうれん草や小松菜をくだものと一緒にミキサーにかけてスムージーにしたりすると、野菜の味が和らぎます。また、かつお節、しらす干し、桜エビ、ツナなど、うまみ成分の豊富な食材と組み合わせることで、野菜の味わいが深まり、子どもも自然と食べやすくなります。

また、少量で必要な野菜を手軽に摂取できる食品を活用するのもおすすめです。たとえば、野菜を凝縮した野菜ソース『ぎゅぎゅっと野菜』は大さじ1杯程度で赤ちゃん(離乳後期~)に与えたい野菜1食分(20~30g)を摂取できます。離乳完了期や幼児期になってもヨーグルトにかけたりスープに加えたりパンに添えたりとアレンジがしやすく、野菜や果物の自然な甘みで不足しがちな野菜の補給にも役立ちます。
『ぎゅぎゅっと野菜』は、子どもが苦手な苦味を抑え、野菜本来のおいしさを引き出した、お子さんにも食べやすい味わいになっています。さらに生後9か月頃(離乳後期~完了期)はまだ奥歯が生えてそろっていないため、繊維の多い野菜は食べにくく、飲み込みにくいものです。そのため、なめらかで、赤ちゃんでも安心して食べられるよう工夫されています。
おすすめ商品 ぎゅぎゅっと野菜
大さじ一杯で1食分の野菜(約10種類)が採れる※1
※1本品は原料野菜・果実の全成分を含むものではありません。野菜摂取の補助としてお役立てください。ごはん・飲み物やおやつにアレンジして食べられる
赤のぎゅぎゅっと野菜


含まれる野菜
-
 トマト
トマト
-
 にんじん
にんじん
-
 赤ピーマン
赤ピーマン
-
 アスパラガス
アスパラガス
-
 かぼちゃ
かぼちゃ
-
 ほうれん草
ほうれん草
-
 キャベツ
キャベツ
-
 ブロッコリー
ブロッコリー
-
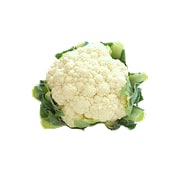 カリフラワー
カリフラワー
オレンジのぎゅぎゅっと野菜


含まれる野菜
-
 にんじん
にんじん
-
 トマト
トマト
-
 白菜
白菜
-
 赤ピーマン
赤ピーマン
-
 アスパラガス
アスパラガス
-
 かぼちゃ
かぼちゃ
-
 ほうれん草
ほうれん草
-
 キャベツ
キャベツ
-
 ブロッコリー
ブロッコリー
-
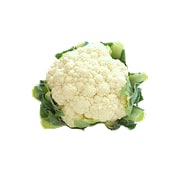 カリフラワー
カリフラワー
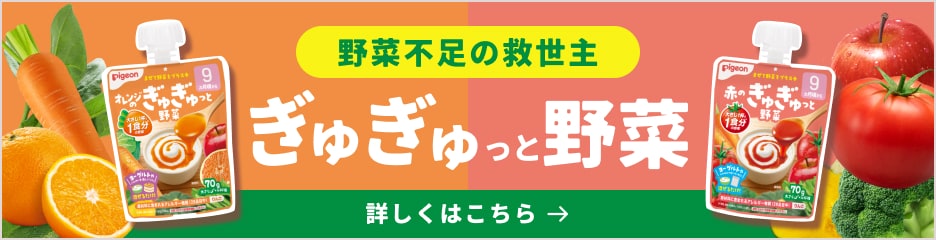
POINT04 食事を出す順番を工夫する

食べさせたいものを一度に食卓に並べてしまうと、子どもは好きなものだけを先に食べてお腹いっぱいになり、苦手なものは「食べなくてもいいや」と感じてしまうことがあります。食事を提供するときには、フルコース料理のように、まず食べさせたい料理を一品ずつ順番に出す工夫をしてみると効果的です。
POINT05 食べたらたくさんほめる

ほめることで、野菜を食べた体験がポジティブに記憶されます。「野菜を食べるとうれしいことがある」というイメージが定着し、次回も前向きに食べようとする気持ちを育てます。また、褒められることで「できた!」という達成感を得ます。これが自信につながり、「また挑戦してみよう」という意欲を引き出します。
POINT06 野菜に親しむ機会を作る
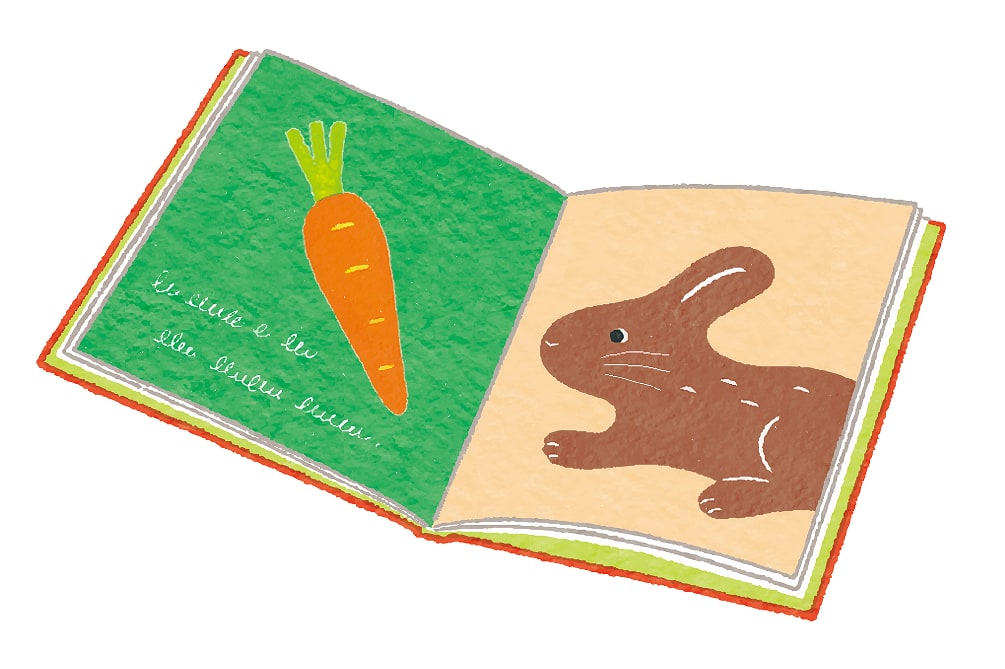
野菜に触れたり見たりする機会が増えると、「野菜は身近で親しみやすいもの」と感じるようになり、未知の食べ物への不安や抵抗感が和らぎます。特に絵本は、視覚や聴覚を刺激しながら、親子の触れ合いを深めることで、子どもが野菜に親しむのにとても効果的です。野菜をテーマにした絵本をぜひ活用してみましょう。
野菜嫌いの克服は、親子で楽しみながら取り組むことがポイントです。無理に食べさせるのではなく、小さな成功体験を積み重ねることで、子どもが自ら進んで手を伸ばすようになるでしょう。今回ご紹介した工夫を取り入れながら、お子さんと一緒に楽しい食事の時間を育んでください。

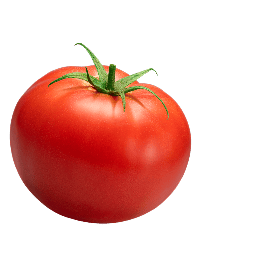
監修

上田玲子先生
管理栄養士・博士(栄養学)・産業カウンセラー
小児栄養学、母性栄養学、栄養教育学、公衆栄養学などさまざまな栄養に関する学問を女子栄養大学、国立公衆衛生院にて学び、栄養コーチングの手法を開発。食を通して子どもの幸せに関わりたいと活動している。帝京科学大学教育人間科学部幼児保育学科教授・学科長を経て現在、白梅学園大学・短期大学非常勤講師。編著に「新版 こどもの食生活」、監修に「人生で一番大事な最初の1000日の食事」(ダイヤモンド社)「はじめての離乳食事典」(朝日新聞出版)「離乳食・幼児食困ったら読む本」(主婦の友社)など多数。