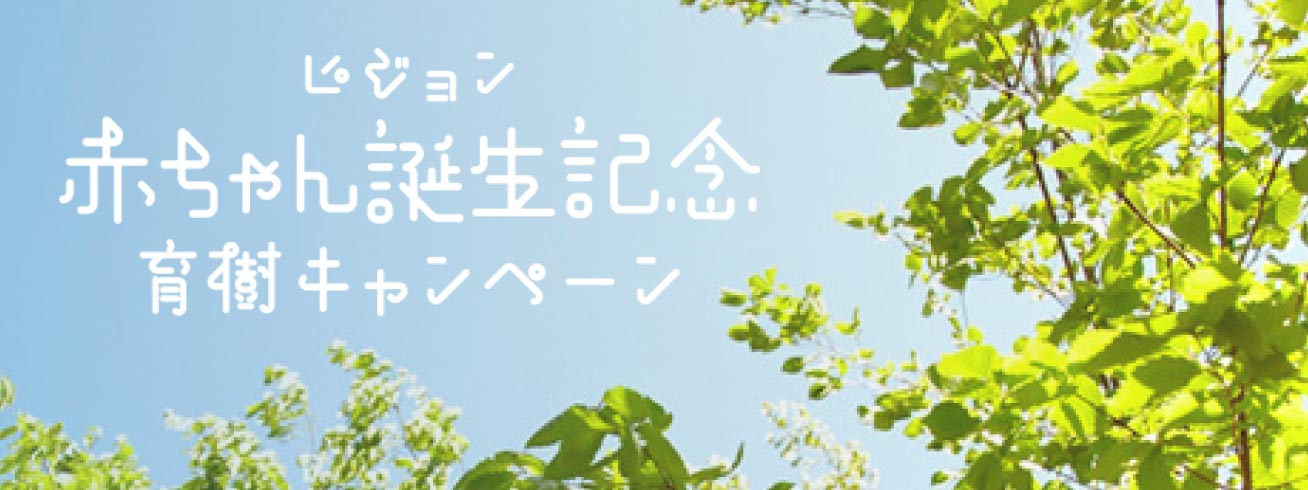離乳食の完了期でいろいろなものを食べられるようになると、「そろそろ幼児食かな?」と考える保護者の方も多いはず。けれど、「いつから始めたらいいの?」「どんなものをあげたらいいの?」と迷う声も少なくありません。
そこで今回は、ピジョンのレトルトパウチシリーズの新商品「保育園の栄養士監修
幼児食」を監修した、保育園を運営しているピジョンハーツの栄養士・須藤先生にお話を伺いました。幼児食を始めるタイミングや基本の考え方、保育の現場での工夫まで、保護者が安心してスタートできるヒントがたっぷり。
さらに、園児たちの試食会にも密着! 子どもたちのリアルな反応や、商品に込められた「食べる力を育てる工夫」も紹介します。

1.
幼児食はいつから?
離乳食との違いとは?
1 離乳食からのステップアップ
離乳食は、生後5~6ヵ月ごろから始まり、主に「飲み込む力」を育てる時期です。やわらかく水分の多い食材を、舌と上あごでつぶしながら食べる段階。一方の幼児食は、1才~1才半ごろからスタートし、咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)・消化など、「食べる力」を総合的に育てるステップへと移行します。
幼児食では、前歯でかじりとり、自分でもぐもぐ噛んで食べるという体験が重要に。自分のペースで手づかみしたり、スプーンを使って食べたりと、「自分で食べること」そのものが成長の一歩になります。

2
幼児食への切り替えは
“その子に合わせて”
幼児食は1才6ヵ月頃~など月齢の目安もありますが、月齢だけで判断せず、子どもの発達に合わせて進めることが大切です。たとえば以下のようなサインがあれば、幼児食へのステップアップを検討してもよいでしょう。
・ 個人差はあるが、歯が上下4本+奥歯が生えてくる頃
・形のあるものを噛んで(口を動かしてもぐもぐと)食べられるようになってきた
・1日3回の食事とおやつのリズムができている
・保育園の食事が幼児食メニューに変わった
ただし、無理に進めるのは禁物。子どもの噛む力や消化機能はまだ未熟なので、やわらかめの固形食から始めるのが基本です。まだうまく噛めずに飲み込んでしまうと、喉につまらせるリスクもあります。
「しっかりもぐもぐ、かみかみして食べること」を繰り返し伝えてあげることも大切。逆に、離乳食を長く続けすぎると噛む力が育たず、丸飲みのクセがついてしまうこともあるため、子どものペースに寄り添いながら、少しずつステップアップしていきましょう。

2. 理想的な幼児食って?
1 幼児食は「食べる力」を育てる食事
幼児食は、単なる栄養摂取の手段ではなく、「自分で食べる」「よく噛む」「味を楽しむ」といった“食べる力”を育てる大切な時間。食材の形や大きさにも工夫が必要で、噛みちぎれるサイズや咀嚼しやすい固さのあるメニューを意識的に取り入れるのがおすすめです。

2 食材と味つけのポイントは?
はじめに取り入れやすい食材は、にんじんやかぼちゃなど、やわらかく煮ることで噛みちぎれるもの。自分の口でかじってみる経験を積むのがよいでしょう。
味つけは、離乳食より少し濃く、大人よりは薄めが基本。お惣菜の半分くらいの味つけが目安です。濃くしすぎると味覚が育ちにくくなったり、消化器官に負担がかかってしまうこともあります。あくまで「素材のおいしさを感じられる味」を大切にしましょう。
3 “家族と一緒に食べる”楽しさも大事
「子どもは大人と同じものを食べたがる」とよく言われますが、実際に「目の前で大人が食べているもの」に強く反応します。だからこそ、家族と同じ時間に、同じ食卓で食べるという体験が、子どもの安心感や意欲につながります。
同じ食材を使って、大人と子どもで味つけを少し変えるだけでもOK。食事は、体の成長だけでなく心を育てる時間でもあるからこそ、親子で一緒に「おいしいね」と笑い合える時間を大切にしたいですね。
3.
保育の現場から学ぶ、
幼児食の安全と工夫
保育現場で多くの子どもと接してきた栄養士ならではの視点から、家庭でも役立つポイントをご紹介します。

1
子どもが“食べたくなる”を引き出す、
給食レシピの工夫
ピジョンハーツでは、子どもの発達に合わせて、食材の大きさや調理法を工夫するのはもちろん、「子どもたちが自分から食べたくなる給食」を目指し、日々のメニューづくりにさまざまなこだわりを込めています。

彩りの工夫
緑・赤・黄色などが偏らないように、見た目の彩りに配慮
味の変化
似た味が続かないように調整し、揚げ物など調理形態も重ならないように工夫
定番メニューの工夫
ハンバーグなら豆腐を混ぜてやわらかく、和風・洋風のアレンジで飽きさせない
郷土料理や海外メニューも取り入れ
「初めての味」に出会える機会をつくる
絵本のメニュー再現
物語の世界とリンクすることで
「食べたい!」気持ちを刺激
2
保育の現場が実践する
幼児食の“安全&やさしさ”ポイント
保育園での豊富な経験をもとに、家庭でも役立つ「安全でやさしい幼児食づくり」の工夫を5つの視点からご紹介します。
1. 肉は“ひと手間”でやわらかく、食べやすく
肉類は繊維が多く、子どもにとっては噛み切りにくい食材のひとつです。そのため、ひき肉をミートボール状にしたり、片栗粉をまぶして加熱するなど、やわらかく仕上がる調理法を心がけています。普通のスライス肉などを使う場合も、繊維を断つ方向に切ることで、噛み切りやすくなる工夫をしています。
2. 骨のある魚は、事前の声かけと“出す練習”を
魚はやわらかくて栄養価も高い優れた食材ですが、「骨がある」という点で苦手意識を持つ子も多いです。大人が事前に「骨があるよ」「見つけたら口から出していいよ」と伝えておくことで、子どもは安心して食べられます。「口から出すのはマナー違反」と思われがちですが、安全のためにはとても大切な行動です。

3. “ぺらぺら食材”は、誤嚥(ごえん)に注意
レタスや海苔、わかめなどの薄くてやわらかい食材は、口の中に張りついたり、喉に詰まりやすい特徴があります。特に海苔は水分で変質しやすく、喉にくっついてしまうと誤嚥(ごえん)の原因にもなりかねません。そのため、刻みのりを使ったり、海苔に小さな穴をあけるグッズを活用するなどの工夫で、安全に食べられるようにしましょう。

4. 小さすぎる=安心ではない。噛む練習になる大きさを
「小さくすれば安全」と思われがちですが、あまりに小さいと噛まずに丸飲みしてしまい、かえって窒息などの危険が高まる場合もあります。噛む力を育てるためには、やわらかく、ある程度の大きさがある形状で提供するのが理想です。また、プチトマトやうずらの卵など丸くて滑りやすい食材は、必ずカットして与えましょう。
5. 食事の“環境づくり”も安全の大切な
ポイント
子どもが泣いていたり、遊びながら食べていたりすると、誤嚥(ごえん)や窒息のリスクが高まります。食事の時間は、なるべく静かで落ち着いた雰囲気の中で過ごすよう心がけましょう。また、幼児食になると食材の形や大きさがしっかりしてくるため、それに伴う安全への配慮もますます重要になります。長すぎると子どもの集中力が切れてしまうため「20分くらいで食べ終えられるリズムを作ること」も、安全に食事を進めるうえでの目安になります。
このように、ちょっとした気配りや準備が、子どもたちの「安全に、楽しく食べる力」につながります。保育園で培った実践の知恵を、ぜひご家庭でも役立ててみてください。
4. まとめ
離乳食が終わって、幼児食へとステップアップしていく時期は、「これで合っているのかな?」と不安になることも多いかもしれません。でも、子どもの成長は一人ひとり違って当然。焦らず、子どものペースに寄り添いながら少しずつ進んでいくことが、何よりの“食育”につながります。
今回ご紹介した、ピジョンの「保育園の栄養士監修 幼児食」は、そんな保護者の不安に寄り添いながら、子どもと一緒に「食べるって楽しい!」を実感できるシリーズです。
「うちの子、これなら食べられた!」「食卓で一緒に笑えた」――そんな小さな成功体験の積み重ねが、子どもの未来の“食べる力”を育てていきます。

須藤妙子先生
ピジョンハーツ株式会社 栄養士
ピジョンハーツが運営する保育施設で、子どもたちが喜ぶ給食やおやつの献立を作成。保育園の栄養士として、食育を家庭にも広げることをテーマに、栽培や調理の体験を親子で楽しめるキットや動画での発信に関心を持つ。野菜嫌いな子が少しでも野菜を好きになるヒントの提案や、忙しい中でも、しっかりとした食事を用意したいママに寄り添うサポートに力を入れています。