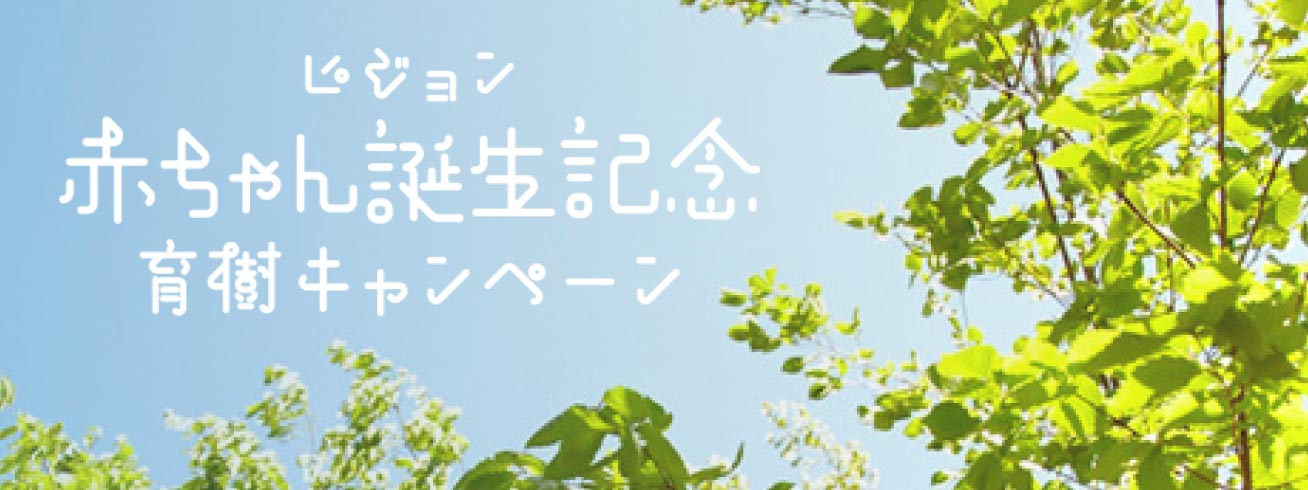乳幼児期のお子さまとデジタルとの付き合い方 ~スマホ・タブレットとの“ちょうどいい距離”を見つけよう〜

多くの保護者が悩む「デジタルとの付き合い方」
「泣き止まないときに、スマホの動画を見せてしまった」
「家事の間、ついタブレットに頼ってしまう」
そんな経験はありませんか?
0才から6才は、脳と視覚機能が目覚ましい発達を遂げる時期です。WHO(世界保健機関)は「2才未満のスクリーンタイムは推奨されない」「2才〜4才のスクリーンタイムは1日1時間未満」というガイドラインを発表しています。
そのため、大切になってくるのはスマートフォンやタブレットなど、デジタル機器と「どう付き合うか」です。この記事では、発達段階に応じた適切な距離感を保ちながら、デジタル機器と賢く付き合う方法をご紹介します。
医師からのワンポイントアドバイス
お子さまは保護者の行動をよく観察しており、私たち大人が日常的にスマートフォンを使用していると、お子さまも同じような習慣を身につけやすくなります。お子さまのデジタル依存や長時間視聴の傾向が気になるようでしたら、お子さまの前では長時間の使用を控えるなど、保護者自身のスマートフォンとの付き合い方を意識してみましょう。
年齢別・デジタル機器との向き合い方
お子さまのデジタル機器との適切な付き合い方や注意すべき点について、年齢ごとにご紹介します。家庭での目安としてご参照ください。
0~6カ月:
ほぼ“ゼロ視聴”推奨
新生児から生後6カ月までの赤ちゃんは、まだ視覚機能が発達途上です。スクリーンの強い光は、発達途中の視覚系に過度な刺激を与える可能性があります。この時期の赤ちゃんが求めているのは、ママやパパの顔、声、温もりです。日本小児科学会の調査では、長時間の視聴が1才6カ月時点での言葉の出現の遅れと関係があることも明らかになっています。
この時期にデジタル機器を見せる場合は数分程度に留め、保護者の方と一緒に見ることが大切です。できるだけカラフルなおもちゃやモビール、音の出る布絵本など、実際に手で触れて五感の発達を促す遊びを優先できるとよいですね。
7カ月~2才:
模倣と自我の芽生え期
周囲にいる人々の行動を真似する「模倣学習」が始まり、言葉や自我が芽生えてくる時期です。ママやパパがスマホを触る姿を真似したがるようになります。WHO(世界保健機関)のガイドラインでは、2才未満はスクリーンタイムを推奨していません。2才では1日1時間以内、少ないほど良いとされています。できるだけ、親子の触れ合いや実体験を優先しましょう。
せっかく真似をできるようになってきたなら手遊び歌や「いないいないばあ」などデジタルがない頃から親しまれてきた遊びがおすすめです。アナログな遊びの楽しさを一緒に育めるとよいですね。
3~4才:
自分で操作したがる時期に
お子さまは自分でスマホやタブレットを操作したがるようになります。しかし、「もっと見たい」「やめたくない」という欲求のコントロールはまだ困難です。
デジタル機器の使用は1日約30~60分以内に制限し、終了時間を事前に約束することが大切です。子供向けアプリを使う場合も、内容について親子で話し合い、実生活で活かす機会を作りましょう。文字や数字への興味が芽生える時期なので、読んだり書いたり、アナログな遊びも楽しめます。
医師からのワンポイントアドバイス
この時期は、お子さまがデジタル機器の使用に夢中になりすぎて、外遊びやごっこ遊びなど従来楽しんでいた活動を嫌がるケースも報告されています。適切な時間制限を設けることで、バランスの取れた遊び体験を保つことが大切です。
5~6才:
学習ツールとしての活用期に
就学を控えたこの時期は、デジタル機器が学習ツールとしての価値を持ちはじめます。ひらがなの練習アプリや、算数の基礎を学べるコンテンツなど、教育的価値の高いものも見つかるでしょう。
ただし、1日約60分以内という制限は守り、必ず休憩時間を挟むことが重要です。この時期から、お子さま自身にもデジタル機器との付き合い方について考える場面を用意し、家族でルールを話し合う習慣を作りましょう。
月齢ごとの成長の様子注意したい4つのシーンと対策

お子さまにデジタル機器を与えてしまいがちな生活シーンと、その具体的な対策をご紹介します。
①食事中・就寝前
食事中は家族との会話を大切にし、就寝1時間前はブルーライトの影響を避けるためスクリーンは禁止しましょう。デジタル機器は別の部屋に置けば、アナログへの親しみもはぐくめます。
医師からのワンポイントアドバイス
就寝前のデジタル機器の使用は、ブルーライトの影響により視床下部でのメラトニン(睡眠ホルモン)分泌が抑制され、眠りが浅くなることが分かっています。質の良い睡眠は、お子さまの成長と発達、様々なホルモンバランスにとって重要な役割を果たしているため、就寝前の使用は特に注意が必要です。
②移動・外出時
長時間の移動時や公共の場では、できれば絵本や手遊び歌を優先し、デジタル機器は最後の手段として短時間利用に留めます。小さな絵本やシールブック、簡単な手遊びのレパートリーなどを事前に準備しておけると良いですね。
③家事・仕事中
家事や仕事に集中したいシーンに向けても、できるだけ事前に準備をしておけると理想です。ひとり遊びができる年齢のお子さまなら、ブロックやパズル、塗り絵など安全に集中できる遊びがおすすめ。
まだひとりで遊べないお子さまなら、抱っこひもやベビーサークルを活用し、近くで作業したり、簡単な声かけや歌を交えたりして過ごすと安心です。
短時間で終わる作業を区切って行うと、親子ともにストレスが少なくなります。
④兄弟や友達と遊ぶとき
3才以降は、デジタル機器の共有ルールを教え、順番を守る練習をしていきます。「5分ずつ交代で」など、事前に子どもたちと一緒にルールを決めましょう。
デジタル機器の「上手な頼りかた」3選
忙しい保護者が罪悪感を抱えずに、デジタルを上手に活用するための3つのポイントをお伝えします。

①質の高いコンテンツ選び
限られた時間でデジタルを利用するのであれば、教育番組のコンテンツや、教育機関が推奨するアプリなど、学習効果が期待できるコンテンツを選びましょう。また、年齢や発達段階に適しているか、暴力的・不適切な内容が含まれていないかの事前チェックも重要です。
②タイマー等を活用した時間管理
デジタル視聴時には、視覚タイマーや音楽で分かりやすく終了時間を予告します。事前予告でアナログへの移行がスムーズになります。「あと5分」「この歌が終わったら」など、お子さまが理解しやすい方法で段階的に伝えることで、デジタル機器から離れる際の抵抗を軽減できますし、決めた時間を守ることで、時間管理の習慣も身につけられるでしょう。
③利用後のフォローアップ
動画やアプリを使用したあとは、お子さまと内容について話し合ったり、見たものを実際に体験できる遊びに発展させたりするなどのフォローアップがおすすめ。受動的な視聴から能動的な学習に変えます。「どれが面白かった?」といった声かけから、デジタルで学んだ内容を現実の遊びに結び付けることで、学習効果を高め親子のコミュニケーションも深まります。
デジタルから他の遊びに誘導する4つのコツ

デジタル機器から他の遊びへの切り替えを、お子さまが嫌がらずにスムーズに行うための実践的な4つのコツをご紹介します。
①やさしい声かけと次の楽しみの準備
「あと5分でおしまいだよ。次は積み木とお絵かき、どっちで遊ぼうか?」と、優しく終了を伝え、次の楽しい活動を一緒に選んでもらいましょう。選択肢を提示することで、お子さまが自分で決めたという満足感を得られ、スムーズな移行が可能になります。また、「おしまい」という言葉よりも「次の楽しいことをしよう」という前向きな表現を使うことで、お子さまの気持ちも前向きに切り替わりやすくなります。
②お子さまの感情に寄り添う
「もっと見たかったね」「楽しかったね」と、お子さまの気持ちを受け止めてから、次の活動に誘います。お子さまの感情を否定せずに共感することで、信頼関係を保ちながら次のステップに進むことができます。「今度また見ようね」など、未来への楽しみも一緒に話すことで、終了に対する寂しさを和らげることができるでしょう。
③環境を整える
視聴が終了したら、デジタル機器を物理的に見えない場所に片付け、新しい遊びに集中できる環境を作りましょう。目に入る場所にデジタル機器があると、お子さまの注意がそちらに向いてしまい、新しい遊びに集中できません。代わりに、次の遊び道具を手の届く場所に用意しておくことで、自然と新しい活動に興味を向けることができます。照明を変えたり、場所を移動したりすることも効果的です。
④デジタルで見たものを実際の遊びにつなげる
デジタル機器で見たキャラクターになりきって遊んだり、同じテーマの絵本やおもちゃを一緒に楽しんだりして、お子さまの興味を自然に次の遊びへと導いてあげましょう。動画で見た動物の真似をしたり、歌った歌を一緒に歌ったりすることで、デジタル体験をより豊かな学びへと発展させることができます。また、画面で見た色や形を実際に探したり描いたりする活動や、ストーリーの続きを親子で考えてみるなど、創造性を刺激する遊びに展開することもおすすめです。
成長段階に合わせたルール作り

この章では、お子さまの年齢に合わせた具体的なルール作りのヒントをご紹介します。
家庭で実践する3ステップ
デジタル機器を完全に禁止するのではなく、家庭の状況に合わせたルールを段階的に作っていくための3ステップをご紹介します。
①現状把握
まず1週間、お子さまのスクリーンタイムを記録し、改善点を見つけましょう。
②年齢別のルール設定
WHOや日本小児科医会の基準を参考に、「○時から○時まで」「1日約○分まで」など、具体的な数値で、お子さまの年齢に適したルールを設定します。
※具体的な年齢別の設定方法については、次の「年齢別ルール作りのポイント」で詳しくご紹介します。
③代わりの遊びを準備
年齢に応じたおもちゃ、絵本、外遊びの計画など、デジタル機器の代わりとなる魅力的な活動を用意します。例えば、粘土遊びやお絵描き、積み木やパズル、ごっこ遊び(お店屋さんごっこ、お医者さんごっこなど)、音楽に合わせた体操やダンス、簡単なお手伝い(お料理のお手伝い、洗濯物たたみなど)といった、手や体を使って楽しめる活動がおすすめです。
年齢別ルール作りのポイント
お子さまの年齢と発達段階に応じて、デジタル機器とのルール作りも段階的に進めていきましょう。
0~2才:
まずは大人がしっかり管理
この時期は、お子さまにルールを理解させるより、保護者が環境をコントロールすることが重要です。使用時間、場所、内容をすべて大人が管理しましょう。
3~4才:
目で見てわかるルールから始める
「長い針が6になったらおしまい」「この歌が終わったらバイバイ」など、視覚・聴覚で理解できるルールを設定します。守れたときは十分にほめてあげて、ルールを守ることの大切さを教えていきましょう。
5~6才:
一緒にルールを決めて自立を促す
この時期には、お子さま自身にもルール作りに参加してもらいましょう。「どうして時間を決めるのか」「守らないとどうなるか」を一緒に考えることで、自主性を育めます。また、決めたルールが守れているかどうかを週に一度見直す時間を作ることも効果的です。
デジタルと上手に付き合う子育てを
デジタル技術は、今や私たちの生活に欠かせないものです。だからこそ、小さなうちから「デジタル機器との適切な距離感」を身につけることが、大切な成長のステップとなります。時にはデジタル機器に頼ってしまう日があっても大丈夫です。親子で一緒に見て、話して、考える時間こそが、お子さまの健やかな成長を支える土台となるでしょう。
監修してくれた先生
 山田克彦
山田克彦
リハビリサポートひうみ 医師・佐世保中央病院 非常勤医師
1990年大分医科大学卒業。1999年より市中総合病院に勤務。
一般小児科診療に加え、学校医として地域の保健活動にも従事。
専門分野:小児科一般・小児循環器・小児肥満・小児内分泌
日本小児科医会「子どもの心」相談医