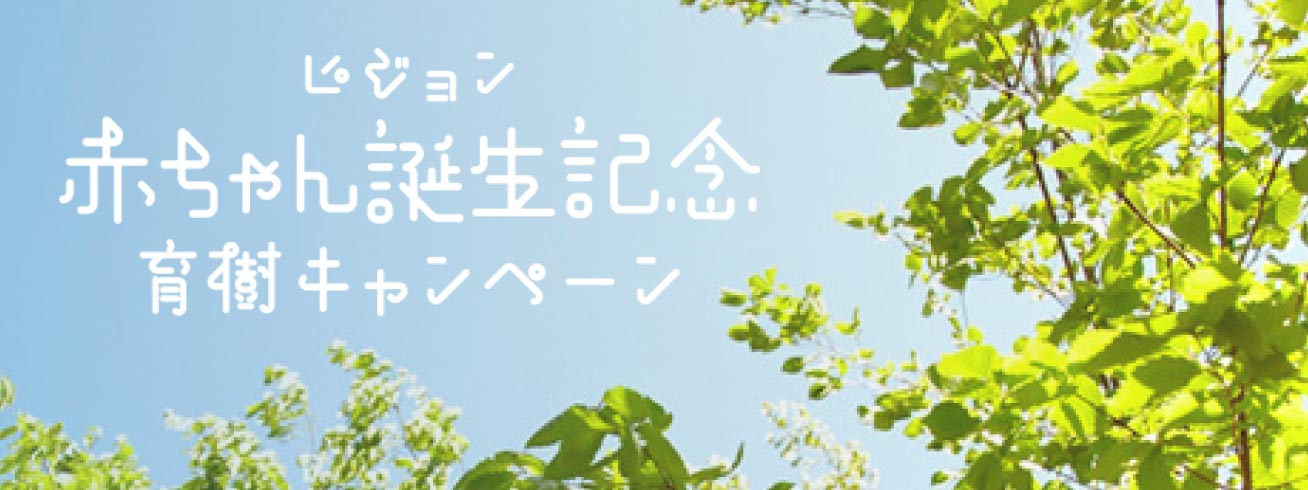赤ちゃんから幼児期の睡眠 ~赤ちゃんから6才までの“ねんね“お悩み解消ガイド〜

睡眠の悩みはみんな同じ?乳幼児期の睡眠の大切さ
ピジョンインフォで2025年5月に実施したアンケート「赤ちゃんの睡眠」(回答838件)によると、その約9割の保護者が「お子さまの睡眠で困りごとがあった」と回答しました。アンケートからは、「夜泣き」や「寝かしつけに時間がかかる」など、多くのご家庭が同じような悩みを抱えておられることがわかります。
睡眠は乳幼児期のお子さまの脳発達や成長ホルモンの分泌、情緒の安定に重要な役割を果たしています。逆に睡眠不足は肥満リスクの増加、学業成績の低下、免疫力低下などをもたらすともいわれています。
この記事では、乳幼児期の睡眠がなぜ重要なのか、そして良質な睡眠を促すための具体的な方法について詳しくご紹介します。お子さまの健やかな成長と、ご家族皆さまの安らかな夜のために、ぜひ参考にしてください。
月齢・年齢別!ねんねの悩みと対策

乳幼児期の睡眠パターンは月齢・年齢とともに大きく変化します。それぞれの時期の特徴を理解して、適切な睡眠環境を整えてあげましょう。
下記図表「各年齢ごとの標準睡眠時間」に記載されている睡眠時間は、夜間の睡眠と昼寝を合わせた1日の総睡眠時間です。夜間の睡眠だけでなく昼寝も含めて、1日トータルでこれくらい眠れていれば大丈夫という目安として参考にしてください。
![各年齢ごとの標準睡眠時間,[0〜3カ月頃]標準睡眠時間:約14〜17時間,[4〜6カ月頃]標準睡眠時間:約12〜15時間,[7〜12カ月頃]標準睡眠時間:約11〜15時間,[1〜2才頃]標準睡眠時間:約11〜15時間,[3〜5才頃]標準睡眠時間:約10〜13時間,[6才頃]標準睡眠時間:約9〜12時間](/sc_rsc/baby/images/theme/early-childhood-sleep-guide/m_pic02.jpg)
0~3カ月:
昼夜の区別がつきはじめる頃
新生児期から乳児期早期にかけて赤ちゃんには1日約14~17時間の睡眠が必要で、昼夜関係なく細切れに睡眠をとります。約2~4時間おきに目を覚ますのが自然な状態です。生後約1カ月頃から徐々に昼夜の区別がつきはじめるため、この時期の環境づくりが重要です。睡眠時間には個人差がありますが、心配せずに見守ってあげましょう。
具体的には、日中は明るく夜間は暗い環境をつくることを心がけましょう。昼間はなるべくカーテンを開けて自然光を取り入れ、夜は照明を落として静かな環境にします。
4~6カ月:
少しずつまとまって眠れるように
この時期は1日約12~15時間の睡眠が必要で、だんだんまとまって眠れるようになってきます。なかには夜間に約6~8時間続けて眠ることができるお子さまも出てきます。昼寝は午前・午後・夕方の1日3回程度が一般的。睡眠サイクルが確立しはじめるこの時期に、連続睡眠を促すための環境づくりにトライしてみましょう。
寝る前の入眠儀式としてスキンシップや絵本の読み聞かせ、お気に入りのぬいぐるみを見つけることなどを導入し、少しずつ自分で寝られる環境・ルーティンづくりを進めてあげましょう。また、昼寝の時間帯を一定に保つことが、生活リズムの確立につながります。
7~12カ月:
あんよの練習で興奮することも
つかまり立ちやはいはいなど運動機能の発達が活発になるこの時期は、1日約11〜15時間の睡眠が必要です。昼寝が1日2回程度に減少する傾向も見られる時期です。
あんよなど体を動かすことが楽しくて興奮したり、ママやパパの姿が見えないと不安になる後追いが始まったりして、寝つきが悪くなることがあります。
同じ理由で夜泣きが激しくなるお子さまもいますが、これも順調に発達している証拠です。
成長のペースには個人差が大きいものですので、心配ありません。
日中にしっかりと体を動かす時間を作り、分離不安が見られても安心感を与えてあげながら毎日同じ入眠儀式を続け、ルーティン化することがポイントです。
1~2才:
「イヤイヤ」がはじまる頃
自我の芽生えが見られるこの時期は、1日約11~15時間の睡眠が必要です。体力がついてきたことはもちろんですが、「自我の芽生えによる就寝拒否」も見られるようになり、昼寝は1日1回(昼食後約2時間程度)になります。これらも成長の証ですので、心配せずにおおらかに見守ってあげましょう。
寝る前には、遊びから入眠へと切り替える方法を工夫しつつ、「どのパジャマにする?」など選択肢を与えて自主性を尊重することがポイントです。この時期も就寝前のルーティンを心がけ、ルーティンの確立を目指していきましょう。
3~6才:
昼寝をしなくても過ごせるように
3~5才児は1日約10~13時間の睡眠が必要で、6才になると約9~12時間の睡眠時間が目安となります。この頃になるとしっかり体力がついて昼寝なしで過ごせるお子さまが増加し、5~6才頃になるとほとんどのお子さまが昼寝をしなくなります。
夜しっかり寝られるよう、日中の活動量を十分に確保し、昼寝をする場合は約30分~2時間程度に調整します。昼寝が長すぎると夜の就寝に影響するため注意が必要ですが、あくまでもご家族にとって無理のないスケジュールで向き合えると理想的ですね。
また、小学校では昼寝の時間がないため、入学する前は昼寝なしでも過ごせるよう生活リズムを徐々に調整していきましょう。
試してみたい!寝つきを良くする「黄金ルーティン」をご紹介

ここでは、ママパパグラフのアンケート結果をもとに、寝かしつけに関するさらなる情報を調査し、役立つ方法をまとめました。
特に効果が高いとされるのが「18時台入浴→20時就寝」のパターン。入浴から就寝まで約1~2時間空けることで、体温の自然な低下が眠気を誘います。入浴時は38~40度のぬるめのお湯に10~15分程度がベストで、湯上がり後の体温が下がるタイミングと眠気のピークが重なることで、自然な入眠を促すことができます。
次に、多くの家庭で効果的だったとされるのが「真っ暗な室内+ホワイトノイズ」の組み合わせ。ホワイトノイズとはすべての周波数帯域の音が同じ強さで含まれている雑音のことで、換気扇の音やテレビの砂嵐の音が該当します。ホワイトノイズを流しながら、遮光カーテン等で光を遮ることで睡眠の質が大幅に向上するといわれています。小さな物音で目覚めやすいお子さまには、扇風機の音や雨音アプリなどの一定した音が効果的で、家の外の騒音をマスキングしてくれる効果もあります。
「毎晩同じ絵本を読む」というルーティンも効果を感じている方が多く、同じ絵本のフレーズが「もうすぐ眠る時間」という脳への合図になる効果があります。
「おやすみマッサージ」は、優しいタッチで緊張をほぐしてリラックス効果を促進するため支持されています。お子さまの手のひらや足の裏を軽くさすったり、背中を「の」の字になでたりすることで、副交感神経が優位になり自然な眠気を促すことができます。
最後に「カーテンの開け閉め」も効果的なルーティンの一つ。朝の光は体内時計をリセットし夜の眠りを促進する効果があります。また、朝は日光を浴び、夜は間接照明を使うことで、人間の体内時計が整いやすくなります。さらに、起床後30分以内に朝日を浴びることで夜間のメラトニン分泌が促され、より深い眠りにつくことができるでしょう。
なかなか寝てくれないときに見直したいポイント

月齢を問わず、お子さまの寝つきを悪くする共通の要因があります。
まず、寝室の環境の不備があげられます。温度・湿度・明るさ・音などお子さまが眠りやすい環境を整えることが重要です。特に夜は間接照明を使用するなどして、明るすぎない環境づくりを心がけましょう。
日中の活動量不足も大きな要因です。日中に適度な活動量を確保することで自然な眠気が生まれるため、年齢に応じた外遊びや体を動かす活動を取り入れることが大切です。
また、睡眠リズムの乱れも見落としがちなポイント。毎日決まった時間に寝起きすることで体内時計が整うため、休日も含めて就寝・起床時間を一定に保ちましょう。
就寝前のルーティンが確立されていない場合、毎晩同じ流れで就寝準備を行うことによって、お子さまの体に「もうすぐ眠る時間」という合図を送ることができます。
最後に、おむつが濡れている、お腹がすいている、暑すぎる・寒すぎるなどの空腹や不快感があると眠れないため、就寝前に基本的なケアを忘れずに行うことが重要です。この時期のママやパパはなにかと大変ですが、お子さまの気持ちに寄り添いながら見守ってあげてくださいね。
睡眠に関するよくあるお悩みQ&A
ここでは、睡眠に関してよく寄せられる質問と、小児科医からのアドバイスをご紹介します。同じような悩みを抱えている保護者も多いので、ぜひ参考にしてみてください。
- Q:夜なかなか寝てくれません。気をつけることがあれば教えてください。
-
A:刺激を減らし、毎日同じルーティンで体内時計を整えることが大切です。
寝る前の1時間は刺激の少ない環境を心がけましょう。ブルーライトは睡眠を妨げるため、この時間帯のスマートフォンやテレビの視聴は控えます。毎日同じ時間・同じ流れで寝かしつけを始め、入眠までの時間を親子で楽しむ時間と捉えてリラックスした雰囲気を作れると良いですね。日中の十分な活動量確保も重要です。
- Q:夜、おっぱいがないと眠れません。どうやって卒業させれば良いでしょうか?
-
A:急がず少しずつ変化をつけて対処し、お子さまのペースに合わせましょう。
多くのママが経験するお悩みですが、心配いりません。おっぱいの時間を徐々に短くする、「おっぱいの後にもう一つだけ」と絵本や子守唄を加える、パパに寝かしつけを手伝ってもらうなど工夫してみましょう。完全に卒業するまでに時間がかかっても焦らず、お子さまのペースに合わせて進めることが重要です。
- Q:昼寝の時間が長すぎる気がするのですが、起こした方が良いでしょうか?
-
A:昼寝が3時間以上続くか、夜の睡眠に影響する場合は、優しく起こしても大丈夫です。
基本的には自然に目覚めるのを待ちますが、昼寝が約3時間以上続く場合や夜の就寝に影響が出る場合は、優しく起こしても構いません。カーテンを開けて自然光を取り入れる、静かに話しかける、家事の音を少し大きめにするなどして、徐々に起きやすい環境を作ってあげましょう。
- Q:なかなか寝ない日が続いて親が疲れてしまいます。どう乗り切れば良いでしょうか?
-
A:一時的な現象として捉え、おおらかに構えることが大切です。
お子さまが寝ない夜が続くと、「何か病気や異常があるのでは」と心配になったり、「自分たちのやり方が悪いのかな」と自分を責めてしまったりしがちですね。でも、心配しすぎなくても大丈夫。乳幼児期の睡眠は成長過程でさまざまな変化を経験することによるもので、一時的に寝つきが悪くなることは自然な現象です。
また、新しい発達段階(あんよ、言葉の習得など)、環境の変化(引っ越し、保育園入園など)、体調の変化などで睡眠パターンが乱れることもありますがこれらも一時的なものです。お子さまの睡眠リズムには個人差が大きいため、「今日は寝ないかもしれないけれど、それでも大丈夫」という気持ちでおおらかに構えましょう。
同時に親が疲れすぎないよう、たくさん息抜きしてくださいね。
医療機関への相談が必要な目安
次のような状態が約1カ月以上にわたって続く場合は、かかりつけの小児科医に相談することをおすすめします。
・寝ている途中に呼吸が止まる
・いびきがひどい
・眠りの質が悪く何度も起きる
・寝入りばなや夜間に身体の異常な動きがある
・日中の眠気が強すぎる
・極度の夜更かしや朝寝坊が治らない
・睡眠・覚醒リズムの乱れで登園・登校が困難になっている
ただし、お子さまの睡眠中の異常行動(寝言、夜驚など)は年齢とともに自然に消失するケースがほとんどです。規則正しい睡眠時間の確保を心がけ、それでも改善が見られない場合には、医療機関に相談するようにしましょう。
親子で始めよう! 良質な睡眠習慣づくり

お子さまの睡眠に関するお悩みに対しては、睡眠環境の改善や、規則正しい寝かしつけの習慣づけ、適度な運動など、まずはできることから始めてみませんか。お子さまの個性やペースを大切にしながら、焦らずゆっくりと取り組むことで、きっと良い変化が見えてきますよ。
監修してくれた先生
 山田克彦
山田克彦
リハビリサポートひうみ 医師・佐世保中央病院 非常勤医師
1990年大分医科大学卒業。1999年より市中総合病院に勤務。
一般小児科診療に加え、学校医として地域の保健活動にも従事。
専門分野:小児科一般・小児循環器・小児肥満・小児内分泌
日本小児科医会「子どもの心」相談医